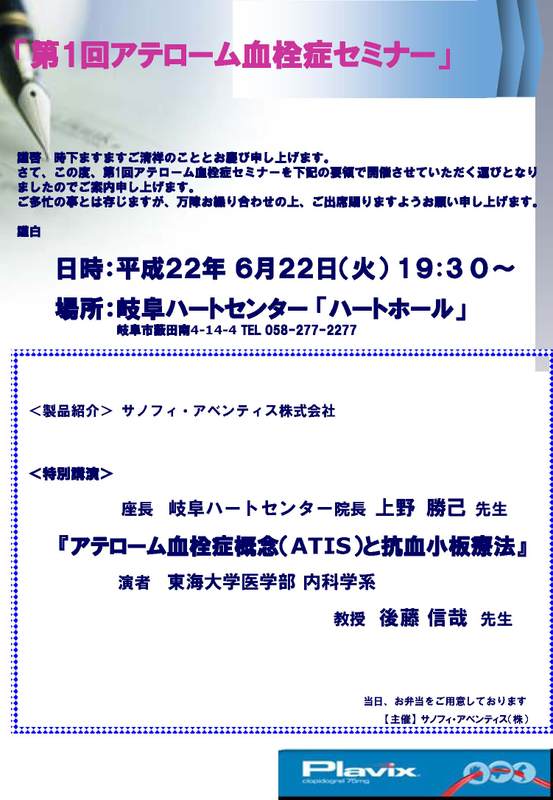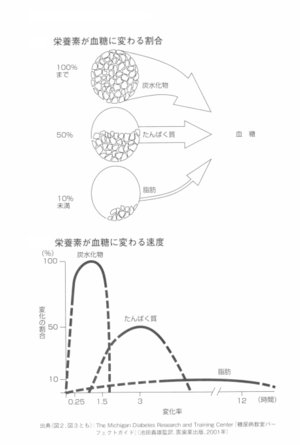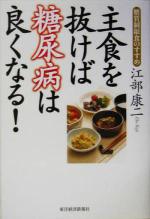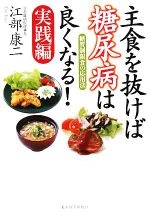平成22年5月7日(金) 岐阜県県民ふれあい会館にて市民公開講座が開催されました。
講演1は


岐阜ハートセンター心臓血管外科部長 富田伸司医師が「サイレントキラーとは?」と題し、大動脈瘤のおはなし.。そのエッセンスは
大動脈瘤は無症状がほとんどで予兆がなく突然発症するのでサイレントキラーと呼ばれます。
原因としては
・高血圧 ・高脂血症 ・たばこ ・糖尿病 ・肥満(メタボリック症候群) ・ストレス ・家族歴
が考えられます。
大動脈瘤を見つけるためには、
・超音波検査 ・腹部CT検査があげられます。
破裂した場合の生還率は25%程度です。
大動脈瘤の発生・破裂を未然に防ぐには、危険因子をコントロールするとともに、もし、見つかった場合には、専門医と相談し、経過観察、治療など、治療計画をすみやかに立てることが重要です。
特に、温度変化が激しい時には、血圧が上昇しないように、注意しましょう。
講演2は

岐阜ハートセンターの循環器内科部長 土屋邦彦医師が「心房細動について」と題し、心房細動について、説明しました。
心房細動は脳梗塞の原因になる。長島監督やオシム監督が心房細動が起因し、脳梗塞になった。この心房細動とは何かを、詳しく説明され、脳梗塞の予防を説明されました。
心房細動は不規則な心室興奮が起因します
①発作性心房細動 ②持続性心房細動 ③永続性慢性心房細動
心房細動の原因と成る要因は
①高血圧、甲状腺疾病、弁膜症、加齢
②飲酒、喫煙、入浴、運動、睡眠不測、過度の緊張、ストレス、発熱も原因になります。
心房細動の症状は
①脈の不整に伴う動悸 ②体動時の息切れ ③血圧低下によるめまい、失神
などがあげられます。
心房細動の治療法は
①薬物療法 ・リズムコントロール
・レートコントロール
②カテーテルアブレーション
まとめとして
①心房細動は心不全や脳梗塞を発症する危険性があり、一見、怖い不整脈だが、適切な抗凝固療法や内服治療でその発症を予防することが出来ます。
②心房細動発生予防には高血圧治療を早期から厳格に行う必要がある。心房が変性、拡大してしまうと再発性で薬物治療抵抗性となりやすいです。
③近年、心房細動の根治的な治療として肺静脈隔離術が施工されるようになり、特に若年者の発作性心房細動については90%程度の有効性があるため徐々に普及しつつあります。
④今後は薬物療法と非薬物療法のバランスを十分に考慮し、個々の患者さんの状況に応じたテーラーメイド治療が主流になると考えられます。
脳梗塞の中でも危険性が高いのは心原性脳塞栓症です。
この心原性脳塞栓症のメカニズムは、心房収縮が低下した結果、左心房内の血液が固まり(血栓)、心房壁に付着した血栓が脳に飛散して発症します。
心房細動と思われたときは、早めに専門医の診察を受けてください。